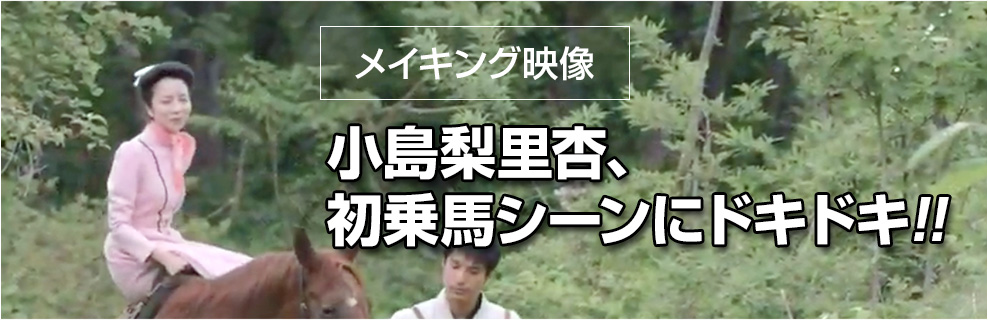メニュー
物語
「この美しい村は大きく変わるかもしれません」──1910年、茨城県久慈郡入四間の裕福な地主の家に生まれ育った関根三郎(井手麻渡)は、ノルウェー人の鉱山技師からそう告げられる。隣村の日立鉱山が大量の銅を生産しているため、煙害が拡大するだろうというのだ。
鉱山から出ている黄色い煙は亜硫酸ガスで、松や杉、栗に蕎麦、大麦小麦など、植物から作物まで何もかも枯らしてしまう。村の権力者である三郎の祖父の兵馬(仲代達矢)は事態を重く見て、分家の恒吉(伊嵜充則)を連れて鉱山会社へ掛け合いに行くが、「補償はするが煙害は我慢してくれ」と言われてしまう。
第一高等学校の受験を控えた三郎に心配をかけたくなかった兵馬だが、ある夜、意を決して「お前にまだ伝えていないことがある」と重い口を開く。30年ほど前、村長として採掘の許可を出したのは兵馬だった。権利料で村が潤い、農家の次男三男の働き口にもなると踏んでのことだったが、今となっては深く後悔していた。「止めねばならん。煙害を、わが関根家の手で」と、遺言のように三郎に告げた直後に倒れた兵馬は、5日後に亡くなってしまう。三郎は祖父の遺志を継ぎ、進学も外交官になる夢も捨てて、煙害と闘うことを決意する。



煙害対策のために設立した入四間青年会の会長に就任した三郎は、まずはカメラを購入して被害の記録を撮り始め、日立鉱山の庶務課長で煙害補償を担当する加屋淳平(渡辺大)と出会う。補償のためなら会社を潰してもいいと断言する加屋に、三郎は口から出まかせを言われたと受け取り、「実に不愉快です」と立ち去るのだった。
日に日に広がる被害を見て、村長(六平直政)は煙害対策委員会を発足し、委員長に三郎を推薦する。引き受けた三郎のもとへ挨拶に現れた加屋は、日立鉱山の社主・木原吉之助(吉川晃司)が、「地元を泣かせるようでは、事業は成り立たない」という信念のもと、煙害の抜本的解決を自ら研究中だと説明する。三郎は加屋の真摯な言葉を信用して態度を改めるが、現場の補償係の八尾定吉(螢雪次朗)に銅山が国策であることを振りかざされ、金で解決するしかないと言われたことには抗議する。
やがて畑が壊滅して借金を抱えた平林左衛門(篠原篤)が自ら死を選び、怒り狂う弟の孫作(城之内正明)に煽られた村人たちは、三郎の制止を振り切って、日立鉱山へ乗り込んでいく。そこでも加屋は誠実に対応し、孫作も突き付けた猟銃を下ろすのだった。
止められなかった自分の責任だと頭を下げる三郎に、加屋は今回の騒動で現金補償の限界を感じ、品種改良した煙に強い苗や種、肥料などの現物補助を検討していると前向きな提案を持ちかける。さらに、加屋の発案と水力発電所の責任者・大平浪三(石井正則)の口添えで、木原が気象観測所を設立することになった。それによって、煙害が拡散しそうな風向きの時は、銅の生産量を抑えることができる。三郎は加屋の計画に感銘を受け、二人は立場の違いを越えて信頼関係を結んでいく。ある時、偶然知り合って心を惹かれた女性が、加屋の妹の千穂(小島梨里杏)だとわかり、3人は急速に親しくなっていく。
 そんな中、政府が鉱毒問題の対策として、全国の鉱山に煙突や煙道の建設を命じる。数ヶ月後、日立鉱山には、政府から派遣された志村教授(大和田伸也)の設計による煙道が設置される。通煙式には、三郎、恒吉、孫作も招待されていた。ところが煙道は大失敗、数十ヶ所の排出口から出た煙の有毒成分が空気で希薄されるはずが、空気より重く降下して一つとなり、三郎たちの村へと流れていった。一度は日立鉱山を信じた三郎の怒りと落胆はあまりに大きく、木原を「あなたは冷酷無情な資本家だ」と責めるのだった。
そんな中、政府が鉱毒問題の対策として、全国の鉱山に煙突や煙道の建設を命じる。数ヶ月後、日立鉱山には、政府から派遣された志村教授(大和田伸也)の設計による煙道が設置される。通煙式には、三郎、恒吉、孫作も招待されていた。ところが煙道は大失敗、数十ヶ所の排出口から出た煙の有毒成分が空気で希薄されるはずが、空気より重く降下して一つとなり、三郎たちの村へと流れていった。一度は日立鉱山を信じた三郎の怒りと落胆はあまりに大きく、木原を「あなたは冷酷無情な資本家だ」と責めるのだった。
煙道が完成すれば、すべて解決すると村の人々に約束していた三郎は、加屋と親しくなりすぎて彼の視点で物事を見ていたと思い至り、加屋には「あなたとはこれきりにさせてください」と宣言する。だが、村へ帰ると、今度は三郎自身が、村を裏切って企業側についていたと疑われ、激しく非難される。
責任をとって委員長を辞任し、ますます深刻化していく煙害を、ただ見ていることしかできない三郎。千穂とも会えなくなり、生きる目的を見失った三郎を立ち直らせたのは、美しい故郷を取り戻したいという強い願いだった──。