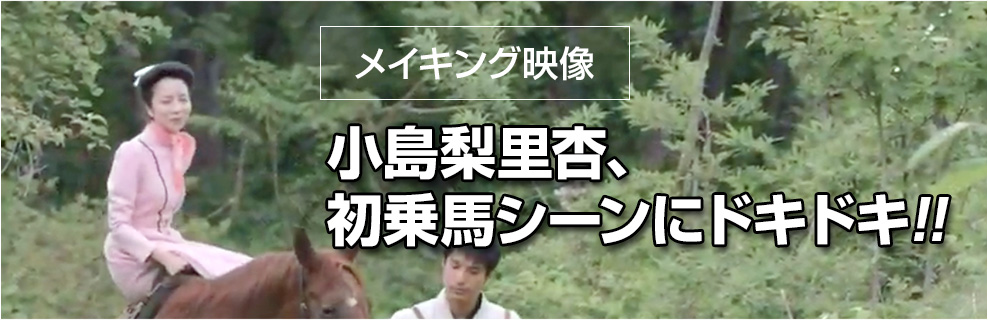メニュー
煙突について

日立鉱山の発展と煙害の深刻化
1905(明治38)年、久原房之助は赤沢銅山を買収し、その名を村名の「日立村」にちなんで「日立鉱山」と改称し、近代的な鉱山の経営に乗り出した。
日立鉱山は、当時の最新技術による探鉱をすすめ、1907(明治40)年末までに、鉱床を次々と発見。銅の埋蔵量の豊かさを確信した久原は、他の鉱山の鉱石を買い入れて製錬することを視野に入れた大規模製錬所建設を計画し、1912(大正元)年までに合計10座の溶鉱炉を完成させた。
しかし、日立鉱山が発展していった一方で、排出される鉱煙の量が増加し、周辺地域の農作物や草木が枯れるなど、予想を上まわる大きな煙害が発生してしまった。
周辺住民に対する補償は、会社の誠意ある対応によって初めは順調だったが、入四間などの製錬所に近い集落における被害は深刻を極めた。
この頃、若くして入四間煙害対策委員長となった関右馬允は、被害の調査や研究をした上で補償交渉をするなど、公平かつ平和的な解決をめざし、奔走した。
煙に強い植物を探して
日立鉱山の庶務課長・角弥太郎は、会社内に煙害などの問題を地元とともに解決する組織である地所係を設置、その試験研究機関として1909(明治42)年に、日立村大字宮田字福内(現在の日立市本宮町域)に農事試験場を設置した。この試験場は、煙と植物の間の因果関係をさぐり、適正な補償に役立てるとともに、優秀な耐煙性植物の開発、苗木の育成などに大きな役割を果たした。1908(明治41)年には、伊豆大島の噴煙地帯にオオシマザクラが自生することに着目した角は、鉱山の社宅周辺へ、オオシマザクラの試験植栽を行っている。
高さ155.7m・世界一の「大煙突」建設
煙害克服のために鉱山はさまざまな方法を検討したが、その道のりは険しいものだった。そのような中、久原は、火山が高く煙を噴いてもさほど煙害をもたらさないことや、日立鉱山の前に携わった小坂鉱山での経験から、煙突を高くすれば煙は悪天候の場合を除いて、ほぼ接地することなく遠方に拡散すると確信していた。しかし当時は、煙をできるだけ薄くし、低い煙突から排出して、煙を狭い範囲に、とどめることが煙害を軽減する最良の方策であると、学者・政府・業界のすべてが信じていたため、久原の唱えた高い煙突による高空への拡散は、受け入れられなかった。久原は部下の反対論を退け、政府を説得し、「日本の鉱業発達のため一試験台」として、「大煙突」の建設に踏み切った。1914(大正3)年12月20日、当時世界一の高さ155.7mの大煙突が完成した。
翌年3月、大煙突から煙が吐き出されると、製錬所周辺ににたれこめていた煙が消え、これを目にした角はのちに「手の舞ひ足の踏むところを知らぬ喜び」と感激を表現している。その後、大煙突と気象観測をもとに炉の操業率を変えて煙の量をコントロールする「制限溶鉱」の対策とあいまつて、煙害は激減していった。
オオシマザクラの植林
農事試験場においては、煙害に強い樹木の研究が続けられ、オオシマザクラ等の苗木育成にも成功した。1914(大正3)年に農事試験場で栽培した.オオシマザクラの苗木の数量は、約120万本と報告されている。
1915(大正4)年3月の大煙突建設によって被害状況が一変すると、角はただちに自然環境を回復させるために、オオシマザクラ、ヤシャブシ、スギ、ヒノキ、クロマツなどの植林を開始した。
その後、約18年に渡る植林の面積は延べ1,200町歩(約1,190ha)に達し、植えられた苗木は、500万本を超える。そのうちオオシマザクラの植林面積は合計595町歩と報告され、約260万本が植林されたと推測される。
日立鉱山による植林とともに、周辺地域の希望者に対する苗木の無償配布も大規模に行われた。1915(大正4)年度の日立村ほか17か村に対する29万本の配布をはじめ、1937(昭和12)年までの23年間に、約500万本の無償配布が行われた。そのうちオオシマザクラの苗木は72万本におよぶと言われている。